死亡したときの年金
年金を受け取っている人が死亡したとき
年金受給者の死亡届をする必要がありますが、マイナンバーを登録していた人は、死亡届を省略できる場合があります。
死亡した人に、まだ受け取っていない年金(未支給年金)があるときは、死亡した人と生計を同一にしていた遺族が受け取れます。
対象となる遺族は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の親族」の順で、最も先の順位の人が受け取れます。
未支給年金の請求手続きをしないで、死亡の翌日以降に振り込みになった年金があるときは、後日お返しいただくことになります。
また、日本年金機構では、死亡した人の確定申告(準確定申告)をする場合に必要となる年金の源泉徴収票を、年金受給者の死亡届を提出した人に送付しています。
共済組合や年金基金から年金を受け取っていた人で、必要な源泉徴収票が届かない場合は、各共済や各基金にお問い合わせください。
国民年金に加入中の人が死亡したとき
被保険者の死亡届は、原則として遺族が手続きする必要はありませんが、国民年金第3号被保険者(会社員や公務員に扶養される妻または夫)が死亡したときは、会社員や公務員の勤務先を経由して、被保険者の死亡届をします。
また、海外在住のため国民年金に任意加入していた人が死亡した場合も、被保険者の死亡届が必要ですので、年金事務所か市役所国保年金係へお問い合わせください。
国民年金の第1号被保険者が死亡したときに、死亡の翌日以降の保険料をすでに納付するなどしていて、払い過ぎになった保険料がある場合には、相続人に還付されます。還付を受けるには、年金事務所で手続きが必要です。
年金を受け取っている人の配偶者や子どもが死亡したとき
年金の受け取りに際し、「配偶者の加給年金」や「子の加給年金」、「子の加算額」(注1)もあわせて受け取っている人は、加算の対象となっている配偶者や子どもが死亡したときは、加算不該当届の手続きが必要です。
注1:配偶者の加給年金は、老齢厚生年金や退職共済年金と、障害厚生年金や障害共済年金に加算されるものです。子の加給年金は、老齢厚生年金や退職共済年金に加算されるものです。子の加算額は、障害基礎年金や遺族基礎年金に加算されるものです。いずれも加算を受けるには条件があります。
そのほかの遺族給付
亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかを受け取ることができます。
詳細は、以下リンクを参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





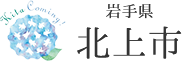
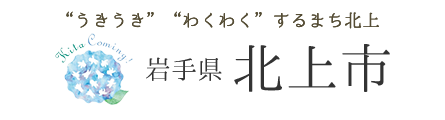

更新日:2023年11月01日