介護サービスを利用するには
要介護認定の流れ
(1)申請
申請が必要なため、長寿介護課に申請してください。
申請は本人または家族が行うことができるほか、民生委員や居宅介護支援事業所などへ依頼して行うこともできます。
申請の際 には、65歳以上の人(第1号被保険者)は介護保険証を、40~65歳の人(第2号被保険者)は健康保険証または医療保険番号がわかるものをお持ちください。
(注意)医療保険番号がわかるものの例…マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」、マイナ保険証を保有している者に交付される「資格情報のお知らせ」、マイナンバーカードを取得していない者等に交付される「資格確認書」など
(2)要介護認定
訪問調査
市の調査員などが家庭を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
調査にあたっては家族の立ち会いや訪問調査事前アンケートの記入などにご協力ください。
主治医の意見書
市の依頼により、主治医が意見書を作成します。
申請書の主治医の欄は申請者が記入してください。
注釈:主治医がいない場合は市の指定する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
(3)結果の通知
二次判定により、要介護1~5、要支援1~2、または非該当の結果が出ます。
結果通知は、申請からおおむね30日以内にお送りします。
注釈:要介護(支援)認定を受けた人が、状態が悪化したり、改善したりした場合は区分変更申請を行ってください。申請書(申請書名:区分変更申請書)は様式をダウンロードしてご利用ください。
介護(介護予防)サービスを利用するときは
- 要介護1~5に認定された人は介護サービス、要支援1~2に認定された人は介護予防サービスが利用できます。
- 在宅でサービスを利用する場合、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を決め、ケアプラン作成後にサービスの利用を開始します。
- ケアマネジャーは下記の居宅介護支援事業所にいますので、要介護(支援)認定を受け、利用したいサービスがあるときはお問い合わせください(参照:市内の居宅介護支援事業所一覧)。
- ケアプランの作成にあたり、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を居宅介護支援事業所経由で長寿介護課へ提出してください。届出書は様式(様式名:居宅サービス計画作成依頼届出書、介護予防サービス計画作成依頼届出書)をダウンロードしてご利用ください。
マイナポータルでの申請が可能になりました
要介護認定について、令和4年4月から、マイナポータルでの申請が可能です。
詳しくは、下記「オンライン申請のご案内」をご覧ください。
マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます!
関連書類のダウンロード
介護保険認定申請書(新規申請・更新申請用) (Wordファイル: 34.1KB)
介護保険認定申請書(区分変更用) (Wordファイル: 28.0KB)
訪問調査事前アンケート様式 (PDFファイル: 289.5KB)
訪問調査事前アンケート様式 (PowerPointファイル: 53.2KB)
注釈)訪問調査事前アンケートはA3サイズで出力のうえご記入ください。
市内の居宅介護支援事業所一覧(R6.4.1現在) (PDFファイル: 77.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





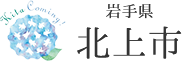
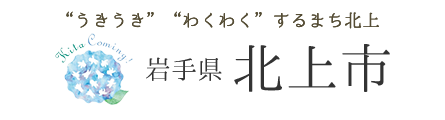

更新日:2025年01月01日