【終了】和賀分館企画展「水沢鉱山展」
地元民に「みんちゃま」と呼ばれ親しまれている水沢鉱山についての展示

JR北上線・岩沢駅からほど近い場所にある水沢鉱山。現在は荒涼とした山ですが、かつては鉱業で繁栄した地です。
その歴史を紹介する企画展を、令和3年12月18日から令和4年3月6日まで行いました。
江戸時代から明治、大正期の日本の発展と近代化を陰で支えた水沢鉱山。
活動の記録を残すため、開催告知時の内容から一部修正して記事を公開します。
水沢鉱山とは・・・?
水沢鉱山は、旧盛岡藩内で最も長く銅の産出を続けた銅山として有名です。
その歴史はさまざまな言い伝えがありますが、寛文元年(1661)に花巻の清水甚兵衛(しみず・じんべえ)が採掘営業を始めた、という記録があります。
江戸時代半ばには、阿部随波(あべ・ずいは)の経営となり全国的に注目されるようになりました。さらに天保3年(1832)の頃になると「日本一の優秀銅板産地」として中国やヨーロッパにも知られるようになったそうです。
明治に入って「鉱山王」と言われた古河市兵衛(ふるかわ・いちべえ)の「古河鉱業」に経営が移ると、機械化や電化によりさらに大きな発展をとげることとなりました。

現在の製錬所付近の様子

製錬所前に打ち捨てられたカラミの山
上の写真は、当時「製錬所」があったあたりの様子を写したものです。
製錬所は乾式冶金設備があり、一日に精銅20トンを処理していたそうです。
最盛期には坑夫等600人の他、きこりや炭焼きなど関連産業に従事する人、運送事業者など非常に多くの人でにぎわい、さらにそれらの家族も含めると3,000人近くの住人がいたそうです。
水沢鉱山は昭和29年(1954)に閉山となりました。
長い間静寂につつまれてきたこの鉱山は、近代化遺産を見直す潮流や地域おこしの観点から近年再び脚光を浴びるようになりました。
いま、市内外を問わず注目を集めています。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





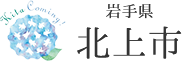
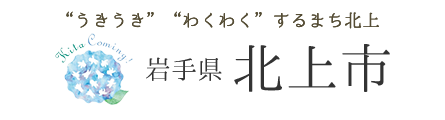

更新日:2022年07月21日