【終了】博物館企画展「會田コレクション 刀と刀装具の魅力」
毎年恒例の刀剣展、今年は刀装具も初展示
北上市立博物館では、令和2年4月11日(土曜日)から5月24日(日曜日)までの会期(途中緊急事態宣言を受けて臨時休館したため、会期を延長しました)で、刀剣にまつわる企画展を開催しました。
当館では毎年桜舞い散る春の時期に合わせ、會田コレクションの刀剣類の中から長曾根虎徹の刀・脇差や新藤国義の刀などを展示してきましたが、今年は初めて刀装具も展示しました。
江戸時代のきらりと光る職人技を堪能できたと好評でした。
以下、記録のために企画展の基本情報や見どころなどを残します。
展示の基本情報
桜花満開刀剣満開 會田コレクション 刀と刀装具の魅力
会期 令和2年4月11日(土曜日)から5月24日(日曜日)まで
会場 北上市立博物館 本館
(展勝地近く、みちのく民俗村となりの白い建物)
開館時間 午前9時から午後5時 (最終入館は午後4時30分)
会期中の休館日 5月11日、12日(施設及び資料点検のため)
観覧料金 有料
交通案内や観覧料金の詳細については、次のリンクからご確認ください!
主な展示品とみどころ
會田コレクションとは・・・?
北上市立博物館の企画展には、しばしば「會田コレクション」の名が冠されたものがあります。
また、来館者の方から「會田コレクションとは何のことですか?」という質問を受けることもあります。
會田コレクションとは、2005年(平成17)に故會田喜一氏のご遺族より一括寄贈を受けた、氏の収集した古美術品などの総称です。會田氏は北上市内で呉服屋を営む傍ら趣味であつめつづけた骨とう品は、絵画や陶磁器、工芸品、刀剣類など多岐にわたります。
物の大小あわせて284点が寄贈され、そのうち刀剣は14点、刀装具類は39点と、氏のコレクションの実に2割近くを占めるものとなっています。
2016年(平成28)に博物館をリニューアルして展示環境が改善されたため、翌春2017年からこのコレクションを活用した企画展を開催しています。春先には刀剣類を、初夏には陶磁器を展示していますので、機会があればぜひご見学ください。
刀装具のみどころ
今年はいつもの刀剣に加えて、刀装具も初めて展示します。
刀剣を携帯するための外装を刀装といい、その部品を刀装具といいます。
刀装の形式は「拵(こしらえ)」といい、太刀拵と打刀拵があります。
拵に付属している部品には、持ち手である柄と刀身の境目にある「つば」、柄の中にしっかりと刀(なかご)を固定する目釘装飾である「目貫(めぬき)」、柄の両端につけられる金具の「縁頭(ふちがしら)」などがあり、太平の世・江戸時代においては武士のお洒落に欠かせないものでした。
その時々の流行や季節感、TPOに合わせた拵を身に着けることは、教養の証でもあったのです。

乙柳軒味墨(いつりゅうけんみぼく)作「早蕨に兎図鐔」
左の画像をご覧ください。これは、江戸時代に作られた鐔(つば)です。
うさぎの丸っとしたおしりが可愛いですね。蕨の新芽と兎の取り合わせが面白く、あたたかな春の陽射しを感じさせます。また、向かって左側に余白を多くとるなど、デザインの面でも優れた鐔です。
作者の味墨(みぼく)は、名工・濱野家の嫡流のみが継承した雅号です。素銅地に思いきり荒目の石目を使っていますが、嫌みがなくさすが名工の作、といったところでしょうか。
象嵌色絵の技法もすばらしく、耳は赤銅数珠覆輪となっています。

脇後藤「松鶴図縁頭」のうち、頭の部分拡大画像
右の画像は、日本美術刀剣保存協会の審査で「保存刀装具」と鑑定された、脇後藤の縁頭のうち、頭のほうを拡大したものです。
頭は、柄をにぎったときに小指側にくるほうの端に取り付けます。腰に下げたとき、相手の目にとまりやすいところですので凝ったデザインのものが多くみられます。
これは金無垢魚子地に高彫のものですが、確かにカズノコのようにつぶつぶとした模様が彫られているのがお分かりいただけると思います。
後藤家は室町時代から幕末期にかけて天下人に仕えた金工師です。一般の需要を受ける町彫りとは一線を画し、将軍家の御用を務めるため家彫りと呼ばれました。後藤宗家は将軍の謁見を許されるなどの好待遇を得、金工界の頂点に君臨した由緒ある家柄です。
分家や分派が多く、14支家が宗家から別れ、これを脇後藤といいます。
その格式の高さからか、将軍家に赴く際には後藤一派の拵を身に着けていかなければならなかったそうです。
デジタルチラシ
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





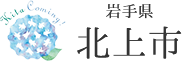
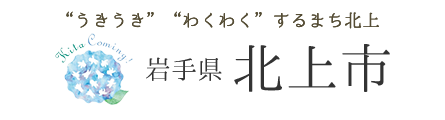

更新日:2020年09月05日