西行
西行(1118~1190)

天保12(1841)年建立
西行は平安末期から鎌倉初期の僧侶で、花(桜)の歌人として広く知られています。俗名は佐藤義清といい、もとは鳥羽上皇の警護にあたる北面の武士でした。
二十三歳で出家し、三十歳の頃、陸奥旅行に出て平泉を訪れています。さらに六十九歳の年には、後白河法皇の命で東大寺再興の砂金を得るため、再び平泉を訪問し、同族にあたる藤原秀衡のもとに滞在しています。
西行の歌集『山家集』には、最初の訪問の際の平泉での作が収録されていますが、県内には他には西行が残したと言われる歌がいくつか伝承されており、この歌 もそうしたものの一つです。『かど(門)岡山』は今の国見山を指し、歌碑は極楽寺開山一千年祭に建立されたと伝えられています。
実際には西行の作かどうかの真偽はともかく、極楽寺を中心とした国見山周辺が、平泉文化に先行して文化の栄えた地であること、そして人々の西行への敬愛の念を、この歌碑は静かに物語っているようです。
(県道 一関・北上線)
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





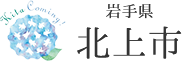
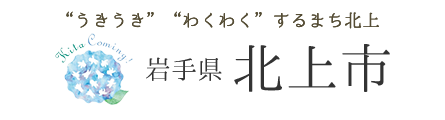

更新日:2019年02月28日