八天遺跡の調査成果を公表します!
調査の歴史
八天遺跡は、北上市更木34地割に所在する縄文時代中期末葉~後期後葉(約4,500~3,200年前)の集落跡です。圃場整備(更木東部開発)に先立つ調査によってその特異な性格が明らかになりました。
第1次・2次調査は昭和43・44年に実施され、この場所に平安時代の役所が存在したのではないかと推定されました。その結果圃場整備は一旦見送られましたが、再び計画が持ち上がり、第3次~5次調査が昭和50~52年に実施されました。この調査では、平安時代の役所は存在しないことが明らかになりましたが、代わりに縄文時代後期の集落跡が注目を集めました。
第4次調査(昭和51年)で、耳・鼻・口形土製品が相次いで発見され、仮面の部品ではないかと考えられました。続いて直径13mを超える大形の円形建物跡が発見され、八天遺跡における縄文集落の特異な性格が注目を集めました。このような調査成果から圃場整備は中止され、遺跡は史跡として保存されることになりました。昭和53年2月22日、遺跡は国の史跡に指定されました。平成20年には、30年ぶりに大形円形建物跡を調査し(第6次調査)、その正確な場所を確認しました。
令和に入って、史跡の適切な保存・活用・整備を見据えて、遺跡の価値を再検討するための発掘調査(内容確認調査)を実施しています。

大形円形建物跡の調査状況(昭和51年)
八天遺跡の調査概要
八天遺跡の調査成果や、令和2年度以降の現地説明会配布資料をPDFファイルで公開します。
パンフレット『国指定史跡八天遺跡』 (PDFファイル: 11.3MB)
これまでの調査成果をまとめたパンフレットです(令和7年3月25日発行)。
令和2年度に実施した第7次調査の成果についてまとめています。
令和3年度に実施した第8次調査の成果についてまとめています。
令和4年度に実施した第9次調査の成果についてまとめています。
令和5年度に実施した第10次調査の成果についてまとめています。
令和6年度に実施した第11次調査の成果についてまとめています。
令和7年度に実施した第12次調査の成果についてまとめています。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





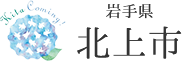
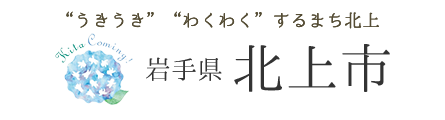

更新日:2025年11月05日