平成31年度発掘調査速報 Vol.3 大堤東遺跡-相去の台地上で初めてみつかった平安時代の古墳-
大堤東遺跡(おおつつみひがしいせき)
所在地:大堤東一丁目 期間:令和元年6月5日~7月9日 調査原因:アパート建設
大堤東遺跡では、縄文時代(詳細時期不明)の土坑1基、平安時代(9世紀後半)の古墳1基、掘立柱建物跡2棟、溝跡1条、時期不明の柱穴状土坑群がみつかりました。古墳からは直径約8メートルの周溝と横90センチメートル、縦180センチメートルの埋葬のための穴2基がみつかっていますが、土を盛った墳丘の有無は不明です。埋葬のための穴が2基作られる古墳は県内には類例がありませんが、掘立柱建物跡も2棟みつかっていることから、両者には何らかの関係があるのかもしれません。9世紀後半に相去の台地上では集落が急増しており、この古墳はそうした集落における指導的な人物の墓だったのかもしれません。

赤丸が大堤東遺跡の調査地点(西から撮影)。遺跡は北側の水田地帯より20メートルほど高い台地上の住宅地内にあります。

調査区の全景写真(西から)です。作業中の人や車と比べて古墳の大きさがわかります。円形の溝(周溝)の内側に人を葬った穴(主体部)が二つ並んでいます。


左:古墳内部の主体部内に人を寝かせた様子(西から)。身長180センチメートル程では膝を曲げないと収まりませんが、当時平均的な160センチメートル前後の身長に合わせ掘られたと考えられます。
右:大堤東遺跡の出土遺物。素焼きの土器である土師器や、登り窯を使いより高温で焼かれた須恵器がみつかっています。また、写真下のような鉄釘や、持ち手の木質が残る小刀の一部といった鉄製品も見つかっています。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





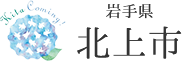
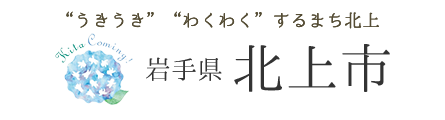

更新日:2020年02月05日