令和2年度発掘調査速報 Vol.6 滝ノ沢遺跡-縄文時代の狩り場と平安時代のムラの跡-
滝ノ沢遺跡(たきのさわいせき)
所在地:大堤北2丁目 期間:令和2年10月8日~11月17日 調査原因:住宅団地造成
滝ノ沢遺跡では過去の調査でも縄文時代の獣を捕らえる落とし穴や、平安時代の竪穴住居跡が複数みつかっています。
今回の調査地点でも縄文時代前期(約6,000年前)の落し穴4基、平安時代(約1,100年前)の竪穴住居跡2棟などがみつかりました。
相去台地では平安時代に入ると多数の村が造られており、今回みつかった住居跡も相去台地を開拓した人々が居住したものとおもわれます。

調査区の空撮写真(画面上が南)です。四角い3つの区画で遺構がみつかりました。画面左側と右下の区画から平安時代の竪穴住居跡、画面右中央と右下の区画から円形や溝状の縄文時代の落とし穴などがみつかりました。


平安時代の竪穴住居跡(ともに南から)です。どちらの写真も、しゃがんでいる人の前方で土が赤くなっています。火を使ったかまどの跡です。

写真は一番大きな区画で見つかった落とし穴の配置を示したもの(南東から)です。人の立っている箇所が円形の落とし穴で、獣道に沿って掘られたとみられます。深さは約70cmです。動物を捕えるため杭を据える小穴を穴の底に掘っているものもあり、小穴も合わせると深さが1m以上になるものもあります。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





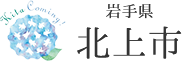
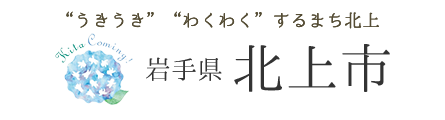

更新日:2021年03月19日