令和3年度発掘調査速報 Vol.1 丸子館-縄文集落と古代の柱列跡-
丸子館跡(まるこだてあと)
所在地:北上市下鬼柳15地割 期間:令和3年5月10日~6月15日 調査原因:集合住宅建設
丸子館跡は中世、天文年間(1532~1544)に一帯を治めた、鬼柳伊賀守の居城と伝えられています。過去の調査により、14~15世紀にかけて造成されたとみられる堀や多数の建物跡、縄文時代、古代の集落跡が確認されています。今回の調査では縄文中期(約4,500年前)の竪穴住居跡や土坑、平安時代(9世紀後半頃)とみられる住居跡、柱穴列跡がみつかりました。このうち注目されるのは平安時代の柱列跡です。3本1組で構成されており、宗教的儀式で用いられる幢幡(どうばん)遺構とみられます。幢幡とは長い竿の先に幡(旗)を吊り下げるもので、毛越寺や秋田城といった寺院跡、城柵跡、都城跡から発見されています。集落跡から2基見つかった例として、秋田県胡桃館遺跡では915年の十和田山噴火に伴う火砕流により、木造建物や柵列と共に幢幡遺構とみられる柱列2基が当時のまま埋没しているのが発見されました。胡桃館遺跡の建物は仏教に関係するとみられており、今回の調査範囲付近にも9世紀後半期の仏教施設が存在している可能性があります。

調査区全景図(南西から) 手前側で人が屈んでいる円形の窪みが縄文時代の住居跡、奥の左端の人がいる場所が縄文時代の貯蔵穴、残る二人がいる場所が幢幡遺構とみられる柱穴列跡です。

縄文時代の住居跡(北西から) 5.0×4.3m程の楕円形で、立っている人の足元に柱穴があります。中央には火を焚いた熱で変色した炉跡があります。

幢幡遺構とみられる柱穴列跡(南西から) 柱穴3基で1組の柱穴列が2か所みつかりました。どちらも3基の柱穴のうち、中央の柱穴には長い柱を据えるためのスロープ状の溝が掘られています。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





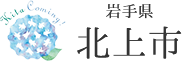
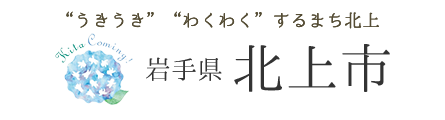

更新日:2024年03月14日