北上市施政方針 令和7年2月
北上市施政方針 令和7年2月(第301回2月通常会議)
令和7年(2025年)第301回2月通常会議が開会され、八重樫市長は2月28日の本会議で施政方針を表明しました。ここでは、その全文を掲載します。
第301回2月通常会議 施政方針 (PDFファイル: 385.0KB)
1 はじめに
本日ここに、第301回2月通常会議が開会されるに当たり、今後の市政運営の方針並びに主要な施策について所信の一端を申し上げ、市議会、市民、企業の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
今年度を振り返りますと、まず第一に言及すべきこととして当市の若者の大活躍がありました。合唱、吹奏楽、民俗芸能、各種スポーツ等での全国における活躍は、児童・生徒自身の努力の賜物であることはもとより、指導に当たった先生方、保護者、関係者の皆様の力を結集した成果であり、心から敬意を表するとともに、市民に明るく楽しい気持ちを与えてくれたことに感謝を申し上げます。また、素晴らしい成果を生んだ背景には、先人たちがまちの将来を見据えて進めてきた人材育成や教育環境向上への取組みとともに、「北上市文化交流センターさくらホール」や「北上総合運動公園」といった活動拠点となる施設の整備にかけた情熱や決断、そして整備後の着実な管理・運営があるものと考えられ、これまでの当市の先駆性や独自性を持った挑戦的な取組みが実を結んでいるものと感じております。
さらに、今年度は「北上線全線開通100周年、鬼の館開館30周年、アメリカ・コンコード市との姉妹都市提携50周年、飯豊小学校創立150周年」など数多くの周年の年を迎え、記念事業等を通して、当市の長い歴史や伝統を改めて振り返り、次の世代に繋げる契機となりました。
私は、市長に就任してから、先人たちがこれまで築いてきたまちづくりの方向性を引き継ぎつつ「“うきうき”“わくわく”しながらもっと住みたいまち」、「人口減少社会においてもキラリと輝き発展を続けるまち」、「若者や女性が生き生きと活躍できるまち」としてより一層発展させ、これからも安心して暮らし続けられる「住みよい北上 住みたい北上」を実現するために、北上市総合計画2021~2030に掲げる各種施策を実行して参りました。
この間、当市を取り巻く社会・経済情勢は、人や物の流れがコロナ禍前に戻りつつある中、物価高騰や生産年齢人口の減少による人材確保などに対応する課題を抱えながらも、市民や企業の皆様、市議会の御理解、御協力により、着実に歩みを進めることができているものと存じております。これまでの皆様の御協力に心から感謝を申し上げます。
特に、今年度は、私の考えを体現する「住みよい北上 住みたい北上推進予算」を編成し、持続可能なまちづくり推進プロジェクトを実行して参りました。
主な取組みを挙げますと、まず、物価高騰に対する地域経済や暮らしの支援として、低所得世帯への給付金の支給や学校給食等に係る食材費高騰対策事業を実施いたしました。
子育て支援施策としましては、子ども医療費助成や保育所保育料軽減の継続実施に加え、こども家庭センターの設置による安心して子育てができる環境整備等に努めて参りました。また、結婚に伴う経済的な負担を軽減するために「結婚新生活支援補助」を開始いたしました。
移住・定住の促進については、都市プロモーション課内に「住みたい北上係」を設置し、ポケモンを活用したシティプロモーションの実施などにより交流人口の増加を図るとともに、移住定住の促進に向けた戦略の構築を行い、今後の取組みにつなげることとしております。また、人口減少が進む地域においても持続可能な地域運営ができるよう、地域づくり課に「和賀・川東地域振興支援室」を設置し、地域の現状やこれまでの施策を分析するとともに、新たな施策の検討や地域づくり組織の支援を行いました。
教育環境の整備につきましては、統合北上中学校建替え工事や飯豊中学校の長寿命化改良工事を進めるとともに、黒沢尻北小学校の長寿命化改良事業への着手などハード面の整備に取り組むとともに、コミュニティ・スクールの活用により、地域との連携による学校教育の推進を行いました。
芸術・文化の分野におきましては、鬼の館が開館30周年を迎え、記念式典やシンポジウム、特別芸能公演等を開催しました。当市の宝である鬼文化を多くの市民と共有し、郷土の文化を市内外に発信しつつ未来に引き継いでゆく契機となりました。
保健・福祉分野におきましては、モバイルクリニックを本格稼働させ、市民が住み慣れた地域で安心して医療サービスを受けられる環境の充実を図りました。また、子ども、高齢者、障がい者などの属性や世代等に関わらず包括的な支援を行う重層的支援体制を盛り込んだ第4次北上市地域福祉計画を今年度策定いたしました。
産業面においては、北上工業団地の拡張整備や北上北部産業業務団地の整備を実施しました。北上北部産業業務団地では、1工区約2.7ヘクタールの分譲を開始したほか、県による「半導体関連人材育成施設」の整備が市も土地を無償貸与する形で協力するなか進められており、産学官連携による半導体人材の育成・確保、更には、地場企業の半導体関連事業への新規参入にもつながっていくものと期待をしております。また、既存の後藤野工業団地や竪川目工業団地では新たな企業が進出し、更なる企業集積を推進しております。
観光面においては、展勝地エリアの一体活用を推進するため、みちのく民俗村に加えて展勝地レストハウス及び展勝地公園に指定管理者制度を導入することといたしました。今後、民間活力を生かし、年間を通しての魅力向上や利用促進を図ることとしております。
拠点形成においては、令和4年3月に策定した未来ビジョンに基づき、柔剣道場等土地利活用事業において、市民武道館の建設工事が完了し、1階に柔剣道場、2階に弓道場が整備され、立体駐車場や賃貸マンション、その他施設の整備が進められております。
諏訪町地区においては、地元の市街地再開発等準備組合と事業施工者が基本協定を締結し、今年夏頃からの工事実施を目指しております。本通り地区では、地元の地権者会等とともに再開発の手法などについて検討を進めております。また、北上駅西口地区においては、グランドデザイン策定に向けた検討を開始するなど、各地区事業の推進を通じて、都市拠点エリアの賑わい創出や交流人口の増加につなげていきたいと考えております。
公共交通については、JR北上線の全線開通100周年記念事業として、北上駅でのトークショー等のイベントや小学生を対象とした体験乗車ツアー等を実施し、市内外の皆様に愛着を持っていただくことを通して、より一層の利用促進を図りました。
交通基盤整備においては、国道4号の4車線化整備や東北横断自動車道釜石秋田線北上ジャンクション江刺田瀬インターチェンジ間の直線化並びに北上金ケ崎パシフィックルート整備の早期実現に向け、国や県等への要望活動を活発に実施いたしました。また、北工業団地周辺の道路整備のため、デジタル田園都市国家構想交付金に係る市の単独要望を国へ行いました。
そして、教育・人材育成・人口減少対策・拠点形成等の多分野にわたる面においては、「地域の発展のための次なる一手」として検討しております「大学設置」について、市議会での議論や市政座談会、市民・企業・団体向けの説明会を行ってまいりました。そこでいただいた御意見や来月のフォーラムでの議論等をふまえて、現在、北上市立大学(仮称)基本構想策定委員会で検討している基本構想を年度内に取りまとめて参ります。
以上が、今年度に実施してきた主な取組みであります。
2 現下の社会経済情勢など
次に、当市を取り巻く現下の社会経済情勢について申し上げます。
コロナ禍を過ぎて、地域活動、経済活動、芸術文化・スポーツ活動など様々な活動が活発に行われるようになり、まちに賑わいが戻ってきていると感じております。また、全国的なインバウンドの増加や、地方移住・二地域居住への関心が高まっております。
一方で、当市の人口の動きとしては、活発な企業活動等を背景に社会増ではあるものの、自然減の影響により緩やかな減少傾向となっており、特にも人口減少地域におけるコミュニティの維持や労働人口の不足が課題となっています。
また、子育て世帯や高齢者世帯などが安心安全な暮らしを送るためのニーズの変化や需要の高まりなどに応じた行政運営上の課題も発生しています。
産業面では、企業進出の活況により製造品出荷額が大幅に増加する中で、地域産業のための人材の確保と育成が大きな課題となっております。管内の有効求人倍率は、国や県を上回って依然として高止まりをしており、人材確保のみならず、人材の定着や生産性向上と合わせた取組みがより一層求められております。
労働者不足を補う形で外国人労働者が増加し、市内の外国人人口は、平成27年には374人でしたが、令和6年7月末には1,300人を超え、約10年で3倍以上となっており、外国人との共生の推進が急務となっております。
自然環境の面では、全国的に豪雨や地震などの災害が激甚化・頻発化傾向にあり、市民の防災意識の向上や地域における自主防災組織等の災害対応力の向上が求められております。
また、クマ・シカ・イノシシなど有害鳥獣による人身・農作物被害が増加しており、対策が急務となっております。
以上のような情勢の下、就任3年目となる令和7年度は、強固な経済基盤の確立と市民福祉の増進に向けて、「住みよい北上 住みたい北上」をさらに推し進めるため、着実に成果を出して参りたいと考えております。
3 市政運営方針
それでは、令和7年度の市政運営の方針について申し上げます。
はじめに新年度予算の概要についてでありますが、令和7年度当初予算は、社会経済情勢や市民ニーズを捉えながら、健全な財政運営の視点も踏まえ、私の考える当市の理想の姿を実現するため、選択と集中により各種施策を更に推進し、その成果への市民の理解や実感を深めていくという「前に進める進化」と「理解・実感を深める深化」を合わせて「『住みよい北上 住みたい北上』シンカ(進化・深化)予算」として編成いたしました。
以下、「住みよい北上 住みたい北上」の実現に寄与する主要な施策について、総合計画基本目標及び基本方針に沿って「持続可能なまちづくり推進プロジェクト」を中心に、主な取組みを申し上げます。
はじめに、基本目標「ひと」-「未来に輝く、未来を創る人づくり」について申し上げます。
基本方針1「未来に輝く人づくり」では、「子育て寄り添いプロジェクト」として、主に、子育て世帯の経済的負担の軽減など、妊娠、出産、子育ての希望を実現する施策について、総合的かつ一体的に取り組んで参ります。
子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、第2子保育料の無償化、第1子保育料の軽減、子ども医療費の助成を継続し、結婚に伴う経済的負担の軽減を図るため、結婚新生活支援補助金も継続して参ります。また、産後の身体的な回復や心理的安定につながる支援の充実を図ることとし、令和7年度からの新たな取組みとして、市内ホテルを活用した「デイサービス型産後ケア事業」を実施して参ります。
基本方針2「未来を創る人づくり」では、「学びの改革プロジェクト」として、主に、地域との連携による学校教育の推進、教育環境の整備に取り組んで参ります。
地域との連携による学校教育の推進については、地域とともにある学校づくりを推進するため、コミュニティ・スクールの仕組みを活かして、学校と地域が連携・協働し一体となって、更なる地域の教育力の向上に努めて参ります。
教育環境の整備としましては、児童・生徒の安全で安心な教育環境を確保するため、全体的に老朽化が進んでいる学校施設等について、市の建築物最適化計画等に基づき、統合北上中学校の建替え、飯豊中学校及び黒沢尻北小学校の長寿命化改良工事など各学校の建替えや長寿命化を計画的に進めて参ります。
また、義務教育終了後の生徒の多様な教育機会を確保するため、新たに、市外から市内の高等学校へ下宿等を利用して通学する生徒等に対し、費用の一部を補助して参ります。
基本方針3「すべての人が活躍できる環境づくり」では、「地域をつくる文化・芸術・スポーツプロジェクト」として、主に、文化財や民俗芸能の次世代への継承と多様な人がスポーツに関わる環境づくりに取り組んで参ります。
貴重な文化財の次世代への継承については、国指定史跡八天遺跡の整備と活用を促進するため、整備の実施設計に着手して参ります。
芸術文化の分野においては、さくらホールのネーミングライツ料を原資とし、市内すべての幼稚園、保育園、認定こども園向けのアウトリーチ事業を行い、子ども達が芸術文化に触れる機会の創出を図って参ります。
スポーツの分野においては、高齢者が継続して生涯スポーツに取り組むための補助事業を創設するとともに、ランフェスきたかみの開催による市街地の賑わい創出と、何度も参加してくれるファン層の獲得を推進して参ります。
次に、基本目標「なりわい」-「挑戦する心を原動力とした力強い地域経済の創出」について申し上げます。
基本方針4「力強い地域経済の創出」では、「イノベーションチャレンジプロジェクト」として、主に、企業誘致・企業集積の促進や地域産業の競争力強化に取り組んで参ります。
まず、企業誘致・企業集積の促進については、昨年から分譲を開始した北上北部産業業務団地について、2工区約8.9ヘクタールも令和7年に追加分譲を開始し、企業集積の促進を図って参ります。
新技術の開発・育成や事業化においては、販路開拓など新たな需要の獲得や、生産工程のDX化、脱炭素の推進など付加価値向上に資する取組に加え、ロボットの導入等による省力化に資する取組を新たに支援するなど、中小企業者の生産性向上の更なる推進を図って参ります。
また、中心市街地等の賑わいづくりとしましては、商店街振興事業費補助金や創業支援事業の活用により、中心市街地の振興を図る取組みを継続して参ります。
観光分野においては、さくらまつりや芸能まつり等のイベントについて、各実行委員会とともに、より一層の盛り上げを図るほか、企業による工場見学等の産業観光の再開の動きを捉え、観光宣伝による誘客や物産振興を推進して参ります。
農林業分野においては、スマート農業や生産性向上につながる機械・機器の導入や森林施業の集約化を支援し、民有林の森林整備を促進して参ります。また、今年度から再開した地籍調査事業については、口内町水押地区から本格的に実施して参ります。
更に、クマ・シカ・イノシシなど有害鳥獣による農作物被害を防止するため、地域と連携して対策を強化して参ります。
基本方針5「多様な人材が働きやすい環境の向上」では、「北上×はたらく」プロジェクトとして、主に、労働力の確保、人材育成、多様な就労の場の確保に取り組んで参ります。
まず、商工業分野では、人口減少下における地域産業のための人材確保として、北上雇用対策協議会を通じた就職支援を専門とする事業者との連携による人材確保や離職予防支援を継続して参ります。また、労働人口の減少が見込まれる中においても、企業活動を維持・発展させるための取り組みとして、IoT製作実習を継続し、省力化や省人化など、人手不足解消に繋がるIT・IoT・デジタル化の専門知識や技術を持つ人材育成を通じた生産性向上支援に取り組んで参ります。
農業分野では、親元などへの就農支援を継続するほか、農業支援センターなどの関係機関との連携や国の補助制度の活用により新規就農者の確保に努めて参ります。また、市内林業事業体が雇用する職員を研修会等に派遣する費用を補助し、高度な技術を有する職員を確保して市内の森林整備を促進して参ります。
福祉分野では、自立支援協議会就労支援部会などの関係機関と連携して、障がい者の就労機会の増進を図るとともに、市内の介護福祉士養成施設と連携し、市内の介護サービス事業所での就労を希望する学生の経済的支援に取り組んで参ります。
次に、基本目標「くらし」-「生きる喜びと生涯安心のくらしをサポート」について申し上げます。
基本方針6「健康と安心の地域づくりの推進」では、「いきいき元気ライフプロジェクト」として、主に、多様化するニーズに対する支援体制の充実に取り組んで参ります。
福祉分野では、障がい者の相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センターを新設するとともに、複雑化・複合化した支援ニーズに対応していくため、既存の相談支援体制と地域づくりの基盤を活かしつつ、包括的な相談支援を充実させる「重層的支援体制整備事業」をスタートさせて参ります。また、地域連携ネットワークの更なる充実や市民後見人の養成を開始することにより、認知症高齢者や障がい者の権利を保護するための体制強化に取り組んで参ります。
健康分野においては、健康寿命の延伸とお互いを支えあう地域づくりを一体的に推進するため、「健康づくりプラン」と「こころの健康づくりプラン」を統合して策定し、市民の健康に資する取組みを進めて参ります。
基本方針7「良好な住環境を支える適切な土地利用と基盤整備」では、「拠点形成・ネットワークプロジェクト」として、主に、都市拠点・地域拠点の形成やネットワークの整備に取り組んで参ります。
都市拠点・地域拠点の形成においては、「未来ビジョン」に基づく「諏訪町・本通り二丁目・北上駅前地区の再開発事業」を準備組合等の関係者とともに推進して参ります。
住み慣れた地域で住み続けられる地域拠点づくりにおいては、通院困難者の医療提供支援として移動診療車を活用したモバイルクリニック事業を継続して実施し、利便性の向上などにより利用促進を図り、市民の通院の負担の軽減に取り組んで参ります。
次に、ネットワークの整備に関しましては、公共交通において、地域公共交通計画に基づき、幹線交通の維持、拠点間及び地域内交通の品質改善に取り組むこととし、試行的に「おに丸号口内線の平日毎日運行」を実施して参ります。
また、全線開通101年目となるJR北上線について、沿線市町及び関係団体と引き続き連携し、更なる利用促進に取り組んで参ります。
次に、幹線・高速道路等の交通ネットワークの整備においては、多くの自治体や民間団体・事業者に賛同いただいている期成同盟会の国や県等に対する要望活動などを中心に、国道4号4車線化の早期完了、秋田自動車道北上西インターチェンジから北上ジャンクション間の4車線化の事業化、北上金ケ崎パシフィックルート整備、東北横断自動車道釜石秋田線北上ジャンクション江刺田瀬インターチェンジ間直線化の実現に向けて引き続き取り組んで参ります。
基本方針8「環境にやさしい、安全・安心な暮らしの形成」では、「私から始める減災プロジェクト」として、主に、自然災害への対策や防災力の強化に取り組んで参ります。
環境対策の面においては、市の取組みの方向性を示す地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定し、カーボンニュートラルに向けた取組みを推進して参ります。また、熱中症予防対策のため、ク―リングシェルターの指定や涼み処の開放を実施して参ります。
防災・減災対策においては、頻発している自然災害の状況を受け、配慮を必要とする障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所の円滑な運営体制を強化して参ります。また、避難行動要支援者名簿の更新や実効性のある個別避難計画の作成・更新を行うとともに、「地域支援者」が安心して避難支援活動ができるよう保険加入による支援などを引き続き行って参ります。
近年増加している豪雨や市街地の都市化により、内水氾濫の危険性が高まっていることについては、注意が必要な箇所を抽出し、対策事業を実施して参ります。
防災力・消防力の強化においては、想定最大規模の降雨による和賀川等の浸水想定区域を反映し、新たに作成するハザードマップの住民説明会や出前講座等を通して、災害危険箇所の周知と理解促進に取り組んで参ります。また、自主防災組織研修会及び自主防災マイスター養成講座を継続実施し、住民の「自助」「共助」の意識の向上に努めて参ります。
消防団に対しては、団の運営に要する費用について、新たに交付金制度を創設し、消防団活動を支援して参ります。
基本方針9「誰もが主体的に参画する市民協働の深化」では、「市民が創るまちづくりプロジェクト」として、主に、多文化共生の推進、市民協働の促進、シティプロモーションに取り組んで参ります。
多文化共生の面では、北上市多文化共生指針の推進体制を強化するため、来年度「北上市多文化共生推進本部」を設置し、本部において指針の進捗管理や改善を行うとともに、外国人人口の増加への対応を庁内横断的に推進します。また、異文化に対する理解の促進を目的としたイベントや日本語教室の開催を通して市内在住の外国人と地域住民との相互理解を促進し交流の場の創出に取り組んで参ります。
市民協働の面では、地域づくり組織が取り組む地域計画の中期見直しにおいて、支援を必要とする地域に対する伴走型支援を行って参ります。
和賀・川東地区の振興支援においては、令和7年度から新たに「集落支援員」を設置し、地域の状況や課題の把握を行い、課題解決に向けた取り組みを進めて参ります。
協働の取組の更なる進展を図るため、まちづくりマッチングフェアの開催など、多様な活動主体の対話や協働を促進する環境づくりに取り組んで参ります。
また、次世代のまちづくり人材の育成を進めるため、地域おこし協力隊を活用しながら、市内の高等学校等と連携した人材育成事業を継続して実施して参ります。
次に、シティプロモーションの面では、令和7年4月に開園予定の「イシツブテ公園in きたかみ」や「ポケふた」などのキャラクターを活用したシティプロモーションを推進し、交流人口の拡大に向けて取り組んで参ります。
また、これまでのシティプロモーションの取組みを評価・検証し次期「都市ブランド推進行動計画」を策定するとともに、「移住定住戦略」で設定したメインターゲットの獲得に向けた取組みを検討し実施して参ります。
基本方針10「まちづくりを支えるしくみづくり」では、「自治体のスマート化プロジェクト」として、主に、効果的・効率的な行政運営及び自治体DXの推進に取り組んで参ります。
まず、効果的・効率的な行政運営については、扶助費の増加や新たな行政需要、物価高騰などへの対応が迫られる中で、将来を見据えて優先課題に対応しつつ、安定した財政運営を行うため、適確な財政状況の分析、新たな財源の確保、事務事業の精査等に取り組んで参ります。
次に、ICTを活用した行政サービスの提供においては、国の施策に準じて、マイナンバーカードと運転免許証の一体化、住民基本台帳・印鑑登録・戸籍等の各種システムの標準化、電子申請・オンライン化などへ対応し、市民の利便性の向上を推進して参ります。
以上が「持続可能なまちづくり推進プロジェクト」を中心とした主な取組みであります。
4 結び
結びとなりますが、少子高齢化や人口減少、物価高騰、担い手・人手不足など、今後も社会経済情勢の厳しさが続くなか、市民生活への支援や地域経済対策などについては、機を逃さずに引き続き、検討・実施していく必要があると考えております。
また、国が昨年12月に示した「地方創生2.0」は「若者や女性にも喜ばれる地方、高齢者も含め誰もが安心して住み続けられる地方」の構築を掲げており、当市総合計画のまちづくりの将来像「“うきうき”“わくわく”するまち北上」の姿にも合致するものであります。今後、より一層、国の動向も注視しながら、持続可能なまちづくり推進プロジェクトを実施して参ります。
また、令和7年度は、総合計画の中間見直しの年になりますので、これまでの成果の検証や社会情勢の変化等を踏まえて、適切な軌道修正等を行って参ります。
私は、任期の折り返しとなる令和7年度も「住みよい北上 住みたい北上」を実現するため、市議会、市民、企業の皆様との協調を大切にしながら、市政を担う者として、地域の将来を見据えて、かつ、挑戦する心を持って、持続可能な活力あるまちづくりを更に進めて参りたいと考えております。
以上、所信の一端を申し述べさせていただきましたが、議員並びに市民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げまして、私の所信表明とさせていただきます。ありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。





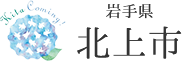
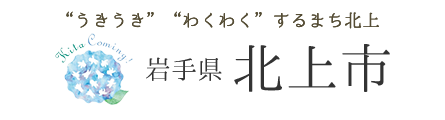

更新日:2025年03月10日